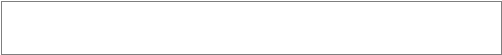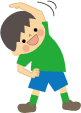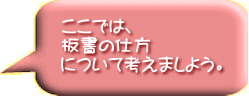○子どもが資料を理解し、考える(補助、活発化、整理、気付く、明確化、振り返る)ための
手助けとして板書を計画します。
○授業の流れが一目でわかる板書は、子どもが考える材料となり、板書を見ることで自分の
考えを整理したり、補強したりすることができます。
○1時間の授業では、ねらいとする価値にせまる経緯(話や授業の流れ)が一目で分かる、
一枚書ききりの板書が理想です。
板書の要素
・資料の内容理解を助ける掲示物(黒板への手書き、短冊、図や写真など)
・発問に関わる図や言葉
・子どもの反応(発言や記述より)
【構造が単純な資料の場合など】
【主人公の変容の前後でも共感させたい場合など】
【高学年〜中学校で扱う資料で、主人公と他の登場人物の対比を考える場合など】
板書例(資料「心のレシーブ」)
手はじめに、上記の3つのパターンを基本形として、板書計画を立ててみましょう。。
また、資料に応じてより適切な方法を選びましょう。
※導入は、資料名の提示の前後どちらにしても、より興味・関心を引き立てられたり、
キーワードの意味をおさえたりできるように計画しよう。
※資料の内容理解を助ける言葉や発問は、あらかじめ短冊に書いておいたり、口頭で
の伝達のみに留めたりすることができます。もちろん、黒板への手書きも可能。
ただし、その方法をとる時間が子どもの活動にとって有効であるように計画してみましょう。
※資料の内容理解を助ける掲示物は、資料の内容やねらいとする価値に沿うものを使用しま
しょう。必ずしも資料そのものの挿絵を使用する必要はなく、より効果的なものを作成する
ことも考えよう。