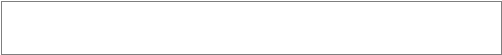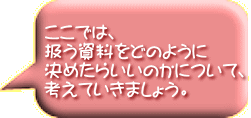1.ねらいの決定
その1時間でできること → 新しい情報、気づき、確認、納得 があるか。
2.資料の選択
ポイント① 内容項目の中のさらに絞り込んだねらいとする価値にせまることができる資料
(例)内容項目「思いやり・親切」
「親切にしてもらううれしさ」か、
「人に親切にするすがすがしさ」か、
「相手のためには、手助けしないことも思いやり」か、
など、扱う資料
「思いやり」のどんな側面なのかを吟味する。
ポイント② 子どもの経験を思い出させ、共感させやすい資料
ポイント③ 子どものこころの奥底まで踏み込み、深く考えさせやすい資料
3.読み物資料の類型
共感型・・・・登場人物の気持ちの変容に共感していくことによって、
ねらいに到達しやすい資料
討議型・・・・登場人物のとった行動や、これからとるべき行動について討議することで、
ねらいに到達
(その行動の基となる心情について深めることが大切)
問題発見型・・登場人物の行動や考えについて問題となる点を発見させ、それを考えていく
ことでねらいに到達しやすい資料
(ねらいとずれないように授業を組み立てることが大切)
感動型・・・・有名人や歴史上の人物、実在の人物やできごとなど、そのできごとや人生を
知り考えることによって、ねらいに到達しやすい資料
(資料を読んで感動しただけで終わらない発問が大切)
4.資料の何に注目するか(共感型資料について 教師のよみ)
①主人公は、何を手がかりとして、何を得たのか、何に気づいたのかを道徳的に見る。
(言動の変化、心理の変化、道徳的価値観の変化)
②主人公の道徳的価値の変容の有無によって、ねらいとする価値へのせまり方を考える
変容がある場合→そのきっかけとなったことと、そのときの心の動きを捉える
変容がない場合→主人公を通して、その資料で扱う価値そのものを考える
起(主人公がねらいとする価値に気づくための条件、人間関係、状況などを把握する場面)
転(主人公が葛藤を乗り越えたり、価値に反する行為を反省することによって高まる場面)
※「転」が中心場面となることが多い。
※資料によっては「結」が中心となるものや、「結」がないものなどもある。
④資料中の言葉
形容詞、副詞(句)に注目 動詞との関連で心理を読み取る鍵となる
⑤時間の推移 行間を読む
描かれていない時間に、どんな心の動きがあったのか 等